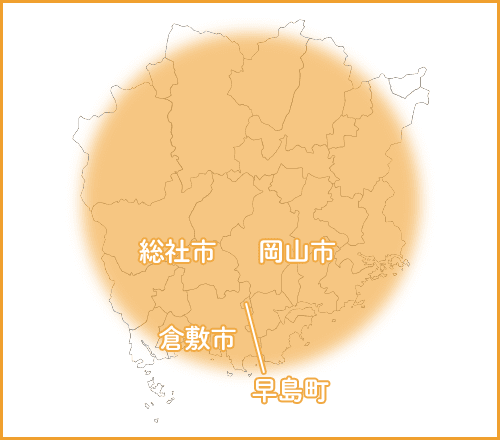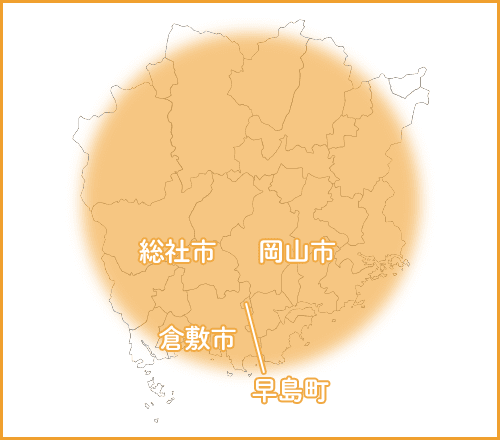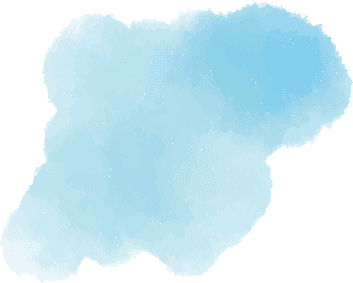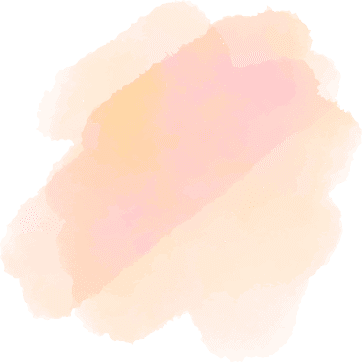倉敷市 バルコニーのシート防水工事が完成しました
- 塗装
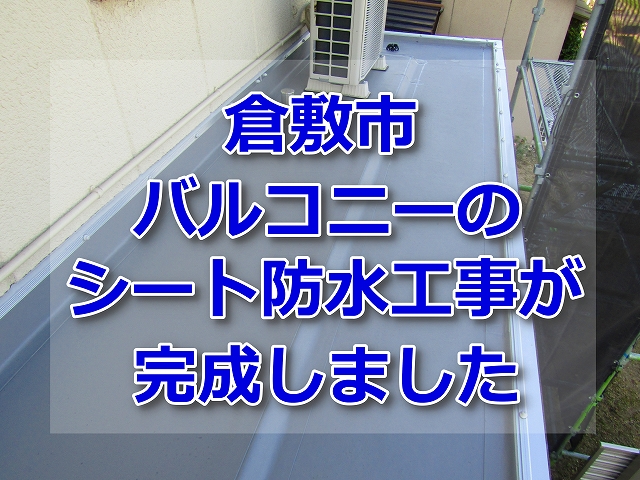
目次

塗装に対する不安やお困りごと、まずは世間話や雑談でも構いません。
ご家族皆さんと向き合うために、
たっぷりと時間をかけてお話させてください。
 086-464-0110
086-464-0110
受付時間: 9:00-18:00 定休日:年中無休
岡山県全域岡山市、倉敷市、総社市、早島町